今回は少し長くなりますが、犬を飼っている方には是非知っていて欲しい情報となりますので最後までお付き合い下さいね。
さて、皆さんも一度はこのような言葉たちを耳にしたことがあるのではないでしょうか。
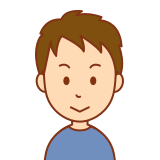
犬にはリーダーが必要だ!
人間がリーダーであるべきだ!!
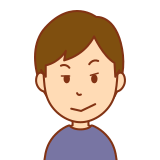
犬に舐められたらいう事を聞かなくなるよ!
舐められたら終わり、しつけは厳しくするべきだ!
果たしてこの言葉は本当でしょうか?
本当だと思っている方は、なぜそう思うのでしょうか。
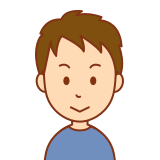
いや、なんとなく昔からいわれているし…
それに犬の祖先はオオカミだろ!?
オオカミの群れにはリーダーがいるって聞いたことがあるんだ。
「なんとなく昔から」
「犬の祖先であるオオカミは群れのリーダーに率いられている」
私も昔はこのように思っていましたし、当時はその根拠について深く突き詰めようとした事はありませんでした。
実際にトレーナーの勉強を始めてからパートナードッグを迎えてトレーニングをする中で
「服従させる」
「言う事を聞かせる」
「従わなかった時は厳しく対応する」
ことをしていった結果、私のパートナーはトレーニングやトリックは出来るけれど楽しそうではないように見えることもしばしばありました。
特に所属していた団体での「マテ」のトレーニングでは犬が動いたら直ぐに駆け寄り「NO」で再び待たせるといったものでした。
トレーナーの犬たちは、横で棒が倒れようが壁に物を投げつけられようが動いてはいけない。
そのように訓練する事を求められました。
この訓練を始めてしばらくすると、私のパートナードッグである晴は「マテ」をかけると逃げるようになりました。
耳を伏せ、しっぽを下げてその場から離れるのです。
私はひどくショックを受けました。
(当時の私は)リーダーとしての資質が無いのかと悩みました。
結局この時は周りのアドバイスでしばらく「マテ」のトレーニングをやめ、晴が楽しいと思えるトレーニングをしていくという事になりました。
最終的には「マテ」のトレーニングも再開し、長時間色々な妨害があっても待てるようにはなりましたが、今思うと最初の教えと結局行った対処法は大きく矛盾していたのです。
この経験を振り返って実感するのは、厳しくする事がリーダーになるという事ではないし、もっといえば私がリーダーになったから晴が待てるようになったのではないという事です。
確かに、昔は「アルファ・ドッグ理論」という説が提言され広まっていました。
この理論はランダムに捕獲したオオカミを動物園の囲いの中で飼育下に置き観察・研究した末に発表されました。
観察をしているとその内に、餌となる肉の分配を特定の犬がコントロールし出したのです。
これをヒエラルキーが形成されていると仮定した学者は、肉を多く食べている(1番初めに肉を食べ始める)犬から順に、
「アルファ(α)」→「ベータ(β)」→「シグマ(Σ)」→「オメガ(Ω)」
と名前を付けました。
このような観察結果から当時の学者は「オオカミは群れを形成しそこには階層が生まれ、強く攻撃的なアルファが他の全てのオオカミを支配している」と考えるようになったのです。
一見「なるほど~」となるこの理論ですが、いつの時代の話かというと1930~1940年代の話なんですよ。発表されたのは1970年ですが。
今は2021年。何と91年も前のことなんですね。
しかし、当然ながら日々科学や研究は進化します。
この「アルファ理論」もその観察方法に疑問や反論が生じるようになりました。
「アルファ理論」を提唱していたDAVIT MECHはこの説の背景にある囲われランダムに連れてこられたオオカミ達だけでなく、自然界のオオカミの群れについても長年観察、研究してきました。
すると、自然界のオオカミが形成する群れは家族で構成されており、親であるオオカミは子を交配して生産するだけでその地位を獲得している事を発見したのです。
さらには野生のオオカミの群れは、飼育下のような激しい敵意や闘争心を見せないことも確認されたのです。
オオカミたちは協力して子育てをしたり、年長者が若年者を育成し守る事で群れを維持させていたのです。
ではなぜ飼育下のオオカミ達には自然界に見られない攻撃性や階級が確認されたのでしょうか。
観察されていた飼育下のオオカミ達はランダムに異なる地域・群れから捕獲されてきました。
そこには豊富な資源はなく、あるのは人から与えられる乏しい資源。
こうなれば、資源を巡る争いが起こるのもうなずけます。
周りは見知らぬ存在、自分が生き延びるためには資源を確保するよりないからです。
そうして、自然界でのオオカミの群れの在り方を確認したDAVID MECHは自ら「アルファ理論」を訂正する発表を行いました。
このことはMECHのHPやYoutubeでも確認する事が出来ます。
アルファオオカミの概念は、人気のあるオオカミの文献に深く根付いています。少なくとも部分的には、1968年に書かれ、1970年に出版され、1981年にペーパーバックで再出版された、私の著書「オオカミ:絶滅危惧種の生態と行動」のおかげです。出版社に出版をやめるようにとの私の多くの嘆願にもかかわらず、現在はまだ印刷中です。本の情報のほとんどはまだ正確ですが、多くは時代遅れです。私たちは過去40年間で、それまでのすべての歴史の中でオオカミについてもっと学びました。
時代遅れの情報の1つは、アルファオオカミの概念です。「アルファ」とは、コンテストやバトルに勝って、他の存在と競争し、トップになることを意味します。しかし、パックをリードするほとんどのオオカミは、子を交配して生産するだけでその地位を獲得し、それがパックになりました。言い換えれば、彼らは単なるブリーダー、または親であり、今日私たちが彼らを「繁殖雄」、「繁殖雌」、または「雄の親」、「雌の親」、または「成体の雄」または「成体」と呼ぶのはそれだけです。
DAVID MECHのHP(http://davemech.org/wolf-news-and-information/)より抜粋
ちなみにこの訂正は2008年、つまり13年前には既に発表されていたんですね。
なのに未だに浸透していないのは、「アルファ理論」に基づいたトレーニング、すなわち支配性を用いたトレーニングに効果があるという考えが今もなお支持されているからなのです。
海外のTV番組でカリスマ的支持を得た某トレーナーは「アルファ理論」を用いたトレーニングを行い、多くの視聴者はそれを見て感動し彼の考え方が流行するようになりました。
その信者たちにより、例えばトイレトレーニングの失敗、ソファやベッドの上に乗る、その他の望まない行動、そしてあらゆる形態の攻撃性はすべて、「支配」に起因する可能性が高いという考えが広く浸透するようになってしまったのです。
人は理由をはっきりさせたがります。
それが原因だと結論づけてしまえば、支配的な「しつけ」に正当性を持たせる事が出来るのです。
そして悲しいかな、そういったトレーニング方法には一定の効果(人にとって困った行動が無くなる)があるのです。
しかし同時に、どこかに歪ができて別の行動に現れたり犬のココロに傷を負わせてしまったりと、犬との健全な関係を築くためにはふさわしくないという事が、現在多くの研究者やトレーナーによって提唱されています。
さらに言うと、犬はオオカミではありません。
人間の手によって交配されていくことにより、オオカミよりも人に親和性を示すようになりました。
また、人間を「同じ種族としての群れ」とは認識していないという事も言われています。
犬同士のコミュニケーションは実に細かく、犬たちは、多くの場面で人間が自分が示すサイン(ボディーランゲージ)を読み取る事が出来ていないという事が分かっています。
そこにあるのは群れという形ではなく、別の種族による共生となるのです。
共生する為に必要なのは、共通のルールと思いやりです。
ルールを共有するのに支配性は必要ありません。
ルールを共有するのに必要なのはコミュニケーションです。
人間が犬のリーダーになる必要はないのです。
この考え方を昔の私が知っていれば、晴との「マテ」のトレーニングはもっと楽しく素晴らしいものになっていたでしょう。
私自身も、もっともっとこの考えが広まって欲しいと願っています。




コメント